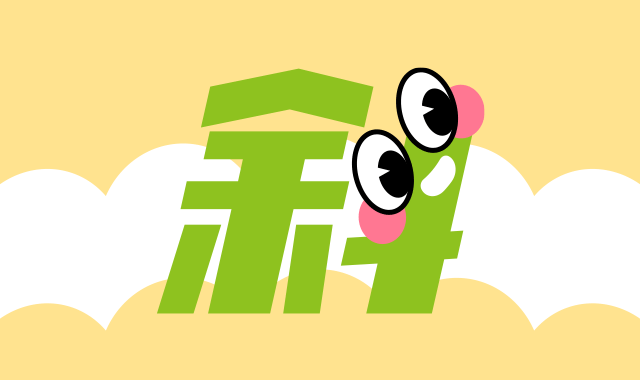吉田修一の小説「怒り」映画化!久々の本格映画に、小説、映画ファンが大注目
吉田修一の小説「怒り」の映画化で実力派若手俳優と渡辺謙が豪華タッグ!
吉田修一の小説「怒り」のモチーフの1つは、外国人女性英語講師を殺害し、自ら整形も施しながら、無人島で暮らすなど、長く逃避行を続けた市橋達也事件です。作中では、千葉の漁港、東京、沖縄の無人島に現れた、細めの逃走犯によく似た謎の男と、彼に関わった人々との物語が展開します。
関わった男や女、その家族や友人は、その男を愛し、信じたいがために苦悩し、やがては自らの過去や秘密さえもが暴き出され、最後は、その誰もが、「怒り」にも似た言い知れない激情をほとばしらせるという物語です。映画や演技派指向の役者であれば、どの役であっても、出演依頼を受ければ、きっと出てみたいと感じる本格作品といえるでしょう。
逃亡犯を思わせる細目の3人の男を、若手演技派の松山ケンイチ、綾野剛、森山未來が演じている映画「怒り」。ほかにも、千葉漁港に住む無垢な女性には宮崎あおい、その父親を渡辺謙が。また、綾野剛を愛する同性愛者を妻夫木聡、無人島の男に興味を持ったばかりに悲劇に見舞われる女子高生を広瀬すずが演じるという豪華なキャスティングは、公開前から大きな話題を呼んでいました。
吉田修一の原作映画「怒り」は人を信じることの難しさ、不条理を描く問題作!
吉田修一の小説は、現代風俗を巧みに取り入れながら、そこに暮らす人々の鬱屈や、日常生活の裂け目が乾いた目線で描かれています。総じて、人を信じることの難しさや、不条理の描写を得意とする作家です。そんな吉田修一原作の映画「怒り」は、封切り後も、前評判を裏切ることなく、好調な動員数を記録しているといいます。
これを聞くと、久々日本映画の衰退が、常套句のように使われていた時代がありましたが、どうやら最近はそうでもないような、あるような……。邦画の公開本数は2000年頃までは、年間300本に満たない状況でしたが、2015年にはその倍近い本数が制作されています。
かといって、映画館に直接観に行っている人が増えているわけではありません。この理由としては、上映メディアの多様化が考えられます。それを下支えしている要因には、制作者・視聴者ともども、その嗜好の細分化があげられるでしょう。ほかにも、現代の邦画を取り巻く環境の変化には、映画の撮影編集システムの軽便化による制作コストの低下や、制作リスクを回避するため、小説や漫画とのメディアミックスが進み、オリジナル作品が少なくなっているなどが見られます。
この変化に伴い、この10年近くの間に、監督やスタッフ、俳優たちも著しく若返りました。そのため、映画会社出身の映画人は、極めて少数派となってきたようです。この秋注目の大作、吉田修一原作、李相日監督の「怒り」も、そういう視点で見ると、また新たな評価ができるかもしれません。
吉田修一おすすめ小説「悪人」映画キャストは?「橋を渡る」あらすじネタバレ!
吉田修一原作で李相日監督のもう1本の映画「悪人」
吉田修一の作品は、決して謎解き・サスペンスといったものではありません。どちらかといえば、人の心の内に切り込んだ重い作品が多いのですが、決して抽象的ではなく、今を生きる人々や風俗を巧みに取り入れられているのが特徴です。クライマックスに向って、ストーリーがテンポよく進んでいくので、読者にとっては、非常にビジュアル的な作風といえるでしょう。
実は、吉田修一原作で、李相日監督の映画作品には、すでに1本、「悪人」が制作されていています。この作品の高評価が、「怒り」の制作へとつながったことは間違いありません。「悪人」もまた、1つの事件としてとらえれば、格差社会、出会い系サイトなど、現代社会に生きる若者のやりきれない暮らしが浮き彫りになります。
しかし、まさに今昔物語「藪の中」に見られるように、永遠のテーマである男女の心の闇が、この「悪人」のテーマであるとも受け取れます。この「悪人」で、不幸にして殺人を犯してしまった青年を演じたのが妻夫木聡。その青年と逃避行する女性を深津絵里が演じています。
また、出会い系サイトで出会い、青年を弄びながら、自らの恋は満たされず激高することによって青年に殺されてしまう女性を演じたのは満島ひかりです。この満島ひかりと、青年と逃避行して最後は青年が意図的に殺そうとする深津絵里、そして愚かな若者を演じた妻夫木聡、本当の「悪人」は、一体誰だったのでしょうか。
吉田修一最新作の「橋を渡る」のテーマの鍵はタイトルの「わたる」
吉田修一の作品には、「怒り」のように、いくつかのストーリーが展開し、それぞれが驚愕のラストを迎えるといったパターンが見られます。吉田修一最新の作品「橋を渡る」は、議会でのセクハラ発言、バンコクで代理出産された赤ん坊たちが保護された事件、女性参議院議員が若いスポーツ選手にキスを強要したスキャンダル、香港での学生たちによる抗議デモなど、誰もが最近見聞きしたことが描かれています。
それぞれは全く関係のないような出来事に、どこにでもいる夫婦や家族、カップルが関わっていくストーリーが第3章まで続きます。そして第4章では、時はなんと2085年の日本に飛びます。そこは、人間とロボットと、それ以外の存在である、たった1人の人間から生まれたサインと呼ばれる者たちがいる社会。現代社会の何気ない事件や出来事が、やがて絡み合い、「橋をわたって」しまうことによって生じる、想像を絶する未来社会が描かれています。
吉田修一としては、初のSF的要素を取り入れた作品ともいえますが、人の業や因果応報、愛憎や不条理といったテーマは、過去、現在、未来を通して普遍のものであるという、吉田修一のメッセージなのかもしれません。
吉田修一VS李相日、原作か映画、どちらが優れているかは愚問
吉田修一原作の映画「怒り」は、公開前から注目度が高かった分、吉田修一のファンからは、辛口の批判もあります。映画がオリジナルストーリーである場合には問題にされませんが、原作があって映画化された作品は、その演出や脚本、キャスティングの良し悪しが問題にされることはよくあることです。
映画「怒り」で主に指摘されているのは、作品のストーリーを忠実に描きながらも、映画終盤、作品のテーマにせまる細やかな書き込みが省略されていた点。また、監督独自の演出が施されていり、作品を読んだ後のほどのカタルシスが得られなかったという意見です。
しかし、映画は時系列の表現であり、一定の共通した理解度を視聴者に要求します。当然、それには、監督の演出力や、俳優の演技力が欠かせません。一方の小説は、読者のスピードで自由に読むことができ、また前後を振り返り、特定場所を深く読込んで反芻することもできます。これはメディア特性の問題といえるでしょう。
少なくとも映画「怒り」は、前作「悪人」の完成度の高さ、満足があってこそ、原作者の吉田修一が、監督である李相日に映画化を託したのであり、その期待は十分に果たされていたのではないでしょうか。また、皮肉に言ってしまえば、原作が良ければ、映画が外れることはまずありません。
映画人にとっては、それが逆に大きなプレッシャーともなります。吉田修一の上下巻合わせて544ページの大作、3つのエピソードが抱えるさまざまな社会問題、そして共通の「怒り」という深いテーマを、142分にまとめ上げた李相日の監督・脚本家としての力量は、評価されるべきでしょう。