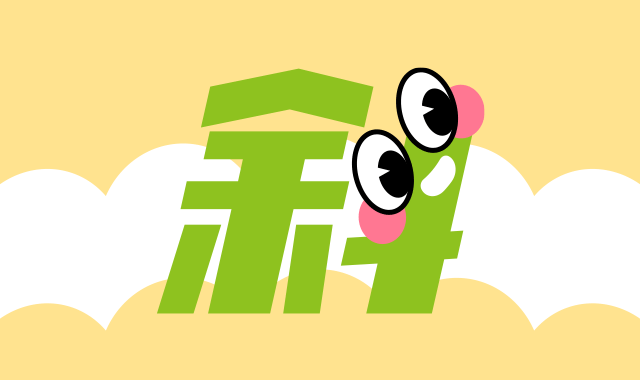谷崎潤一郎作品「細雪」あらすじネタバレ!四姉妹のモデルは?
谷崎潤一郎の「細雪」は何度も映画やドラマ、舞台化された晩年の代表作
谷崎潤一郎は、明治から昭和中期にかけて活躍した文豪です。谷崎潤一郎の小説「細雪」は、戦時中に書き続けられ、戦後1949年に出版された作品で、谷崎潤一郎の代表作の1つ。これまで何度も、映画やテレビドラマ、芝居となり、美人実力派女優の登竜門ともいえる作品となってきました。
「細雪」は、戦争の足音が迫る1936年から1941年までの大阪を舞台にした、船場で暮らす四姉妹の物語。船場の格式ある商家のしきたりと伝統に守られながら、四季折々に色めく四姉妹の、奥ゆかしくも華麗な暮らしぶりが、淡々と描かれています。姉妹たちの会話は全て、今はもう死語となってしまった美しい船場言葉で書かれており、まるで古典の宮廷物語を読むような格調と、滅びの儚さを備えた作品です。
谷崎潤一郎「細雪」のモデルは船場の大店の御寮人様だった松子夫人とその姉妹
谷崎潤一郎作品「細雪」のあらすじは、その美しさゆえに行き遅れた三女・雪子の縁談話や、四女の奔放な恋愛の顛末が、四季を通じて描かれています。この四姉妹には、実はモデルがいました。それは、実際に船場の大店の御寮人様であった、谷崎潤一郎の3人目の妻・松子とその姉妹です。「細雪」では、船場の御寮人様として品格をたたえた次女の幸子が、松子にあたるとされます。
また、幸子の娘の悦子は、谷崎潤一郎と松子の実の娘・恵美子であったとも。谷崎潤一郎は、松子との交際を通じて、伝統と格式を重んじる船場文化と、その姉妹の優雅な暮らしぶり、また、谷崎潤一郎自身と松子との道ならぬ恋を四女・妙子の恋愛模様に模して小説としました。
谷崎潤一郎作品「刺青」あらすじはどう解釈する?映画化の歴史!
谷崎潤一郎作品「刺青」の猟奇的ともいえるあらすじ
谷崎潤一郎作品「細雪」が、王朝物語のような風格を持つ作品とすれば、「刺青」は、明治の文壇を驚愕させた問題作といえます。「刺青」のあらすじは、若く美しい女の肌に魅入られた、元浮世絵職人の彫り師・清吉が、駕籠の簾からこぼれた美しい白い足の娘を見初めるところから始まります。
娘を家に連れ込んだ清吉は、男たちの屍骸に魅せられる若い女を描いた「肥料」という絵を見せた後、麻酔で眠らせて、彼女の肌に巨大な女郎蜘蛛の刺青を彫りました。眠りから覚めた娘は、一転魔性の女に変身。「お前さんは真っ先に私の肥料になったんだねえ」と清吉に語りかけるという、極めて猟奇的な内容で、性的主導権の転倒や、フェティシズムなど、性的倒錯の深淵が描かれています。
谷崎潤一郎は、その後も、「秘密」や「卍」「痴人の愛」など、さまざまな性的倒錯をテーマにした作品を、次々と世に問うています。
谷崎潤一郎作品「刺青」で背中に絡新婦の入れ墨を入れたのは大映きってのトップセクシー女優・若尾文子
谷崎潤一郎作品「刺青」は、ビジュアルイメージを極めて刺激する作品ですが、センセーショナルな内容で、さすがに戦後になるまで、映画化することはできませんでした。1966年に、大映が増村保造監督により初めて映画化が実現。巨大な絡新婦(じょろうぐも)を背中に彫られる女・お艶は、すでに「瘋癲老人日記」や「卍」などの谷崎潤一郎作品に出演し、当時、30歳を過ぎて、こぼれるような色気を放っていた若尾文子が演じました。
その後も、「刺青 IREZUMI」(1984年)や「刺青 SI-SEI」(2005年)から、2009年「刺青 匂ひ月のごとく」まで、谷崎潤一郎の「刺青」をモチーフにした映画は数作ありますが、映画としての完成度の高さでは、増村監督保造作品が一番でしょう。
谷崎潤一郎が川端康成より前に受賞していたかもしれないノーベル文学賞
谷崎潤一郎は、1958年、1960年から1963年にかけてと、1964年も、ノーベル文学賞候補になっていたことが2015年の情報公開により分かっています。中でも1964年は、日本から谷崎潤一郎、川端康成、三島由紀夫と、詩人の西脇順三郎の4人がノミネートされ、谷崎潤一郎は、最終の受賞候補に残っていたそうです。
1960年代当時、戦後復興を果たした日本の文学が、日本文学の研究者であるドナルド・キーン博士や、ライシャワー駐日大使などの尽力により、世界から大いに注目されていたことが分かります。しかし当時は、日本固有の文化や死生観、細やかな抒情表現などが、なかなか外国人には伝わりにくかった面もあったかもしれません。
結局、日本人初となるノーベル文学賞は、1968年に、川端康成が受賞しました。谷崎潤一郎の場合は、性倒錯を扱った作品も多く、キリスト教圏のモラルに反する作品として、忌避されたとも考えられます。日本国内においても、谷崎潤一郎は、今でこそ、日本を代表する文豪と賞されていますが、デビュー当時は、先輩作家が顔をしかめる異端の耽美派でした。
自らの乱脈な女性関係や、奔放で倒錯した性を小説にした、スキャンダル作家であったことは間違いありません。谷崎潤一郎は、21世紀の今こそ、読み直され再評価されるべき小説家といえるでしょう。